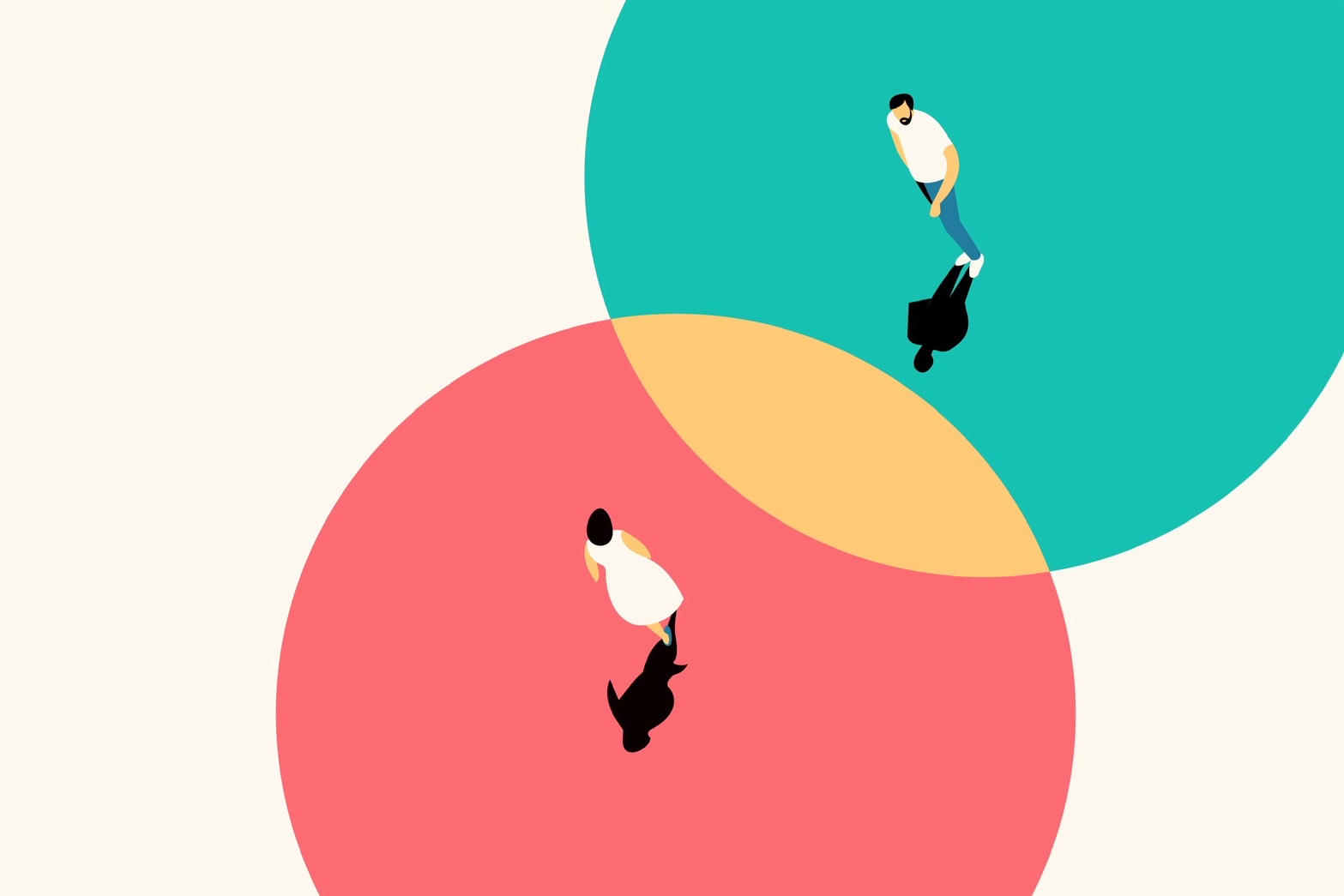アソブロックには、「報酬宣言制」という制度があります。
シンプルに言えば、「自分で自分の報酬を決める」ということ。そんなことを言われたら「もらえるだけ欲しい」と思うのが人間のさがですから、適切に、豊かに決めていくためのしくみがあります。
アソブロックでは、会社のお金のやり取りがつまびらかに公開されています。誰がどのくらいお金を会社に入れているのか、会社の維持・運営にはどのくらいのお金がかかっているのか。そんなことを全て把握し、自分や会社のキャパシティも可能性も考慮に入れた上で、自身の来期の給与を宣言するのです。
▶︎具体的な方法は、過去に社長が解説しています。
https://note.com/danasobu/n/n36b8e5b8453f
アソブロックは、現在23期目。今期は多くのニューフェイスがいたこともあり、制度が適用されていませんでした。筆者である熊谷も、ニューフェイスのひとり。社長から「報酬宣言制を来期から復活させよう」と言われるまで、その存在は感じつつも、その実態がどうなっているのかは知りませんでした。
そして6月のある日、その全容を知ります。すると、簡単には理解ができず、落とし込みもうまくいかぬ。もうすぐ期末はやってきそう。さて困った。
ということで、ひとまず「こんな制度が始まるらしいっす!」と、メンバーみんなに説明して回ることにしました。その過程でいろいろと考え、模索した記録を(未熟ですが)よかったらご覧ください。
◯月×日
社長から「以前は、こんなしくみでやっていた」と教えてもらう。「これを踏襲してもいいし、違うしくみにリメイクしてもいい」とも続けられた。
お金の動きがつまびらかに公開されていくと、自分たちのはたらきによって、この会社がまわっていくのだということを本当によく感じ、よくわかった。自然と「それにしては、わたしは実力のない人間なんだな」「会社を支える人間になりたいな」と心が動く。
◯月×日
Sさん(同期)と話した。自分たちにいかに実力がないかを、同じ温度感で共有できたのがうれしかった。「ずっと給料のところが見えなかったことに、モヤモヤしていた」とも言っていた。そうそう、「この●万円ってどこから?」「このお茶は“出していい”と言われたけど、どこから出しているの?」「月1晩餐会のお金って、どこから?」と、わたしも思っていた。その働きづらさは、やっぱりあった気がする。
「がんばらなきゃいけないのがよくわかった」と、Sさんは続ける。この心の動きが、しくみのもたらすもっとも面白い効果のひとつかもしれない。
◯月×日
Iさん(同期)と話した。話せて良かったのは、「それでも(こんなに大変そうなのに)なぜ、アソブロックにいたいと思うか」ということ。わたしにもわたしなりの理由があるし、他のメンバーそれぞれにもそれぞれのものがある。Iさんとは、こんなことでもないとこんな話はしなさそうだ。交換しあえたのがうれしかった。宣言をするときには、みんなのそれを、みんなが知り合える時間があるといい。
◯月×日
みな、このしくみを知らずに1年間仕事をしてきたメンバーだから、説明をしていく中で、「そんな感じなら、いち抜けた!」とするひとが現れても、おかしくないんじゃないかという恐れを感じていた。(そんなことにはならないだろう、と同じくらいの強さで思っていたものの。)
みんなに思うように生きてほしいけど、協力者がいなくなったら困る。わたしはここでがんばりたいから。下心に近いこの気持ちを、他者に押し付けても永続性がない。が、でもほんとにいなくなってしまったら、わたしは自分の人生をつまらなく思いそう。
10年後、20年後に、自分(たち)の足で立っているために、いまの先輩たちに自分(たち)の稼ぎから給料を出せるような自分(たち)であるために。できることは、「若手同士での積極的なブラック化」と「互いへのケア」を両立することではないかと考える。
◯月×日
Mさん(先輩)と話した。「あ、そんなしくみになってたんだ。ごめんごめん」「じゃあこんなこともできるよね」というような反応をもらう(そういう言い方はされていないけど)。そう言える大人なんだな、かっこいい。行動を変えたら、会社を支える側にまわれる道筋が見えているからこその発言だと思った。
一方のわたしは「無い袖を振ります」としか言えない。ないところから袖を作って、はやく振って、またつくる。頼りないイメージしか持てず、実態が伴わない。「でもめちゃくちゃ袖を振ります」と、威勢を張ることしかできない。これを実力不足という。
◯月×日
あるひとが「“自分は世界の一部である”って感覚が、いちばんのよろこび」だと言っていたのを思い出す。わたしはそれに同意していて、そして、この報酬宣言制のしくみは、世界というには狭い(?)いち会社の一部として、自分(たち)はあるのだ、という感覚をよく実感させてくれるものだと思う。こうした存在への肯定の仕方を、わたしは支持したい。
自分が他者に負っている責任範囲が意外とある、とハッとする。それが会社というものの面白さなのかもしれない。知らんけど。とにかく、そういう存在が人生においてできることは、豊かだなあと思ったりする。「寄付と運動でまわる会社」の、その芯が少しずつ見えてきた。
今度は、寄付の対象者全員で話したり聞いたりする場を行う予定です。
模索は続きます(また更新します)。
文責:熊谷